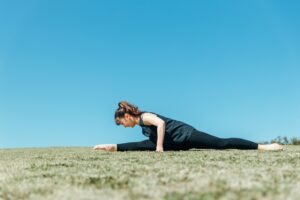見過ごされがちな「坐骨神経痛」の正体とは?
あなたは、足にかけて走るような鋭い痛みやしびれに悩まされた経験はありませんか?
それがもし「坐骨神経痛」であれば、早めの対処が重要です。
坐骨神経痛は一時的な疲労やストレスではなく、神経への圧迫や筋肉の緊張など、深刻な体の状態が背景にあるケースが多いのです。
特に、長時間のデスクワークや運動不足、姿勢の乱れがある方は要注意。
近年では、30〜50代の女性を中心に「慢性的な腰の痛みや足のしびれがあるが、病院に行くほどでもない」と放置してしまい、悪化してしまうケースが増えています。
放置することで、慢性化・歩行障害・生活の質の低下に繋がるリスクもあるため、自己判断せず正しい知識を持って向き合うことが求められます。
この記事では、「坐骨神経痛ってそもそも何?」という基本から、症状の見分け方、セルフチェック、整体での対処法、生活習慣の見直し方法までを幅広くカバーしています。
日常に潜む坐骨神経痛の原因を丁寧に解説しながら、ご自身でできる対策やストレッチ、再発予防の生活改善法まで網羅しています。
「なぜこの痛みが続くのか」「病院に行く前に自分でできることはあるのか」と感じている方にとって、この記事がヒントになることでしょう。
あなたの健康な日常を取り戻すために、まずは坐骨神経痛の正しい知識から始めてみませんか?
目次
1. 坐骨神経痛とは何かをわかりやすく解説2. 坐骨神経痛の主な原因と症状の見分け方3. 坐骨神経痛が及ぼす日常生活への影響4. 専門家がすすめる坐骨神経痛のセルフチェック法5. 整体で改善を目指す坐骨神経痛のアプローチ6. 坐骨神経痛と関連する腰痛の違いについて7. 運動不足が坐骨神経痛を悪化させる理由8. 坐骨神経痛に効果的なストレッチ方法を紹介9. 市販薬と整体を併用した坐骨神経痛ケアのポイント10. 坐骨神経痛の再発を防ぐ生活習慣の整え方
1.坐骨神経痛とは何かをわかりやすく解説
坐骨神経痛は、腰から足先にかけて広がる坐骨神経が何らかの原因で刺激または圧迫されることで起こる、痛みやしびれなどの症状を総称したものです。
医療用語としての正式名称ではなく、症状を表す表現である点が特徴です。
たとえば、坐骨神経自体に病変があるわけではなく、腰椎や筋肉、関節など他の組織の不調が神経に影響を与えることで生じます。
坐骨神経は人体で最も太く長い末梢神経で、腰椎から始まり、臀部、太ももの裏側、ふくらはぎ、足の裏まで通っています。
そのため、坐骨神経痛の症状は広範囲に及び、鋭い痛み、電気が走るようなしびれ、感覚の鈍麻、筋力低下、歩行困難など多岐にわたるのが特徴です。
この症状は中高年に多く見られますが、近年では若年層にも増加傾向があります。
特に長時間のデスクワークや座りっぱなしの生活習慣が原因となり、腰椎椎間板ヘルニアや梨状筋症候群などを発症することで坐骨神経に負荷がかかりやすくなっています。
坐骨神経痛を理解するうえで重要なのは、「病名ではない」という点です。
実際には、神経を圧迫している要因に応じて、治療方法やアプローチも変わってきます。
たとえば、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などが原因の場合と、筋肉の過緊張や骨格のゆがみが原因の場合では、必要な対処も異なります。
さらに、坐骨神経痛は慢性化しやすく、生活の質を大きく低下させる要因にもなります。
国民生活基礎調査(厚生労働省)によると、腰痛は日本人の自覚症状の中で常に上位に位置しており、その中に坐骨神経痛を含むケースが多くあります。
加齢や体重増加、運動不足、冷えなど、日常の小さな積み重ねが引き金になるため、予防と早期対応が重要です。
坐骨神経痛という言葉に捉われず、その背後にある本当の原因にアプローチする姿勢が、正しい改善への第一歩となります。
症状に心当たりがある方は、早めに身体の声に耳を傾け、根本的な対処を検討することが大切です。
2.坐骨神経痛の主な原因と症状の見分け方
坐骨神経痛の主な原因は、腰椎椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・梨状筋症候群の3つが代表的ですが、実際にはそれ以外にもさまざまな要因が存在します。
原因の特定には医学的な知識と検査が必要な場合もありますが、症状の特徴を知っておくことで、自分自身でもある程度の見分けが可能です。
まず、腰椎椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛は、椎間板の中にある髄核が外に飛び出し、神経根を圧迫することが原因です。
このタイプでは、特に20〜40代の比較的若年層に多く見られ、腰を曲げたり長時間座る姿勢を取ったときに痛みが増す傾向があります。
前屈がつらいのが特徴です。
一方、脊柱管狭窄症は高齢者に多く、脊椎の中を通る神経の通り道が狭くなることで、神経が圧迫されます。
立っていると痛みやしびれが出るものの、前かがみになったり座ったりすると症状が和らぐことが多く、「間欠性跛行」という症状が見られます。
これは、しばらく歩くと足のしびれや痛みが強くなり、少し休むとまた歩けるようになるという繰り返しの状態です。
また、梨状筋症候群は、骨盤の奥にある梨状筋という筋肉が硬くなり、直下を通る坐骨神経を圧迫することで生じます。
このケースでは、長時間座っているとお尻から太もも裏にかけてしびれや鈍痛が出やすくなります。
特にデスクワークや運転が多い人に起こりやすいのが特徴です。
これらの違いを見極めるためには、痛みの出る姿勢や状況、しびれの部位、時間帯などを記録しておくとよいでしょう。
また、両足に出る場合は糖尿病性神経障害や内臓疾患など、神経以外の原因も疑う必要があります。
さらに、最近の研究では、ストレスや自律神経の乱れが坐骨神経痛に影響を与えている可能性も示唆されています。
交感神経の過剰な緊張によって筋肉がこわばり、それが神経の圧迫につながるケースもあるのです。
したがって、原因を正確に見極めるには、画像診断や専門的な問診だけでなく、ライフスタイルや心理的要因の見直しも必要です。
複合的な視点で自身の症状をとらえることが、的確な改善策を選ぶカギとなります。

3. 坐骨神経痛が及ぼす日常生活への影響
坐骨神経痛は単なる「足のしびれ」や「腰の痛み」にとどまらず、日常生活全体に深刻な影響を及ぼします。
慢性的な痛みにより、動作が制限され、精神的なストレスや社会的な孤立につながるケースも少なくありません。
まず影響が顕著に現れるのは、移動や姿勢の変化に関わる動作です。
歩行中に脚の痛みやしびれが出て、長距離を歩けなくなる。階段の昇降が困難になる。立ち上がる動作がつらい。こういった問題が日々の生活の中で頻繁に発生します。
特に通勤や買い物、子どもの送迎といった日常の中で、身体の自由が奪われることで自立性が低下していきます。
さらに、仕事への影響も無視できません。
立ち仕事・座り仕事のどちらにおいても、坐骨神経痛があると集中力が続かず、パフォーマンスが著しく下がります。
仕事中の姿勢制限や休憩の必要が増えるため、同僚との業務分担や評価にも影響を及ぼすことがあります。
実際に厚生労働省の調査によると、腰痛による労働損失は年間3兆円を超えるとも試算されており、その一部は坐骨神経痛が原因です。
また、家庭内の役割にも影響が出ます。
子育て中の親であれば、子どもを抱っこしたり、床に座って遊んだりすることが困難になります。
高齢者であれば、家事や介護の役割を果たすことができなくなり、配偶者への負担が増えるケースもあります。
精神面にも悪影響があります。
慢性的な痛みが続くと、うつ状態や不安障害といった心理的問題を引き起こすリスクが高まります。
痛みの恐怖から動くこと自体がストレスとなり、結果として運動不足→筋力低下→痛みの悪化という悪循環に陥りがちです。
このように、坐骨神経痛は放置すればするほど生活のあらゆる場面に悪影響を及ぼします。
したがって、痛みを我慢せず、早期に根本原因を見つけてアプローチすることが、生活の質を守るうえで非常に重要となります。
症状が軽いうちから、体を動かす習慣や正しい姿勢の意識を持つことが、再発予防にも大きく役立つでしょう。
4. 専門家がすすめる坐骨神経痛のセルフチェック法
坐骨神経痛は進行すると日常生活に大きな支障をきたすため、早期発見が非常に重要です。
医療機関に行く前に、自分自身である程度症状を把握しておくことで、適切な対策や施術につなげやすくなります。
ここでは、専門家が推奨する自宅でできるセルフチェック方法を紹介します。
まず注目すべきポイントは、症状の出ている部位とその感じ方です。
坐骨神経痛の場合、多くは片側の臀部から太もも、ふくらはぎ、足先にかけて痛みやしびれが広がることが特徴です。
この範囲に沿って症状が出ている場合は、坐骨神経への影響を疑うべきサインとなります。
また、長時間同じ姿勢を保っていると悪化し、体勢を変えると緩和されるような症状が見られる場合も、神経圧迫の可能性が高いとされています。
次に確認しておきたいのが、脚の動作に伴う痛みの変化です。
たとえば、仰向けに寝た状態で片脚を伸ばしながら持ち上げる「SLRテスト(Straight Leg Raising Test)」があります。
足を約70度程度まで上げたときに、腰から足にかけて痛みやしびれが強くなる場合は、坐骨神経が刺激されている可能性が高いとされています。
このテストは自宅でも比較的安全に実施できますが、無理は禁物です。
また、足裏の感覚の変化も重要な指標となります。
坐骨神経が圧迫されることで、足裏の一部、特に小指側やかかと周辺の感覚が鈍くなったり、冷感を感じたりするケースがあります。
ペンや綿棒などを使って左右の足裏を触り比べると、感覚の違いを確認しやすいでしょう。
近年の研究では、坐骨神経痛の初期段階で反射速度が低下する傾向があることが報告されています。
たとえば、アキレス腱反射が鈍くなる、膝を打ったときの反応が左右で異なるといった現象が確認される場合は、神経伝達に問題が生じている可能性があります。
これらは医療機関での詳細な検査が必要な項目ではありますが、気づくことができれば受診の目安になります。
心理的な兆候にも注意が必要です。
痛みが続くことで無意識に患部をかばい、体全体の動作パターンが崩れてしまうと、痛みの悪化や別の部位への負担にもつながります。
そのため、歩行姿勢や立ち上がり時のバランスの変化に注意を向けることも、早期発見に役立ちます。
坐骨神経痛のセルフチェックでは、「どこが、いつ、どう痛むか」という観察が何より重要です。
違和感を感じたら放置せず、記録しておくことが症状の把握や医師・施術者への相談時に役立ちます。
日々の小さな変化を見逃さない姿勢こそが、重症化を防ぐ第一歩です。

5. 整体で改善を目指す坐骨神経痛のアプローチ
坐骨神経痛に対する改善方法の中でも、近年注目されているのが整体によるアプローチです。
痛みの原因が骨格の歪みや筋肉の過緊張によるものであれば、薬や手術に頼らずとも改善が見込めるケースは多くあります。
特に、長期間にわたって慢性化している場合や、病院で異常が見つからない「原因不明のしびれ」に悩む人にとって、整体は有効な選択肢となり得ます。
整体の基本的な考え方は、身体全体のバランスを整えることで自然治癒力を高め、神経の圧迫を緩和することにあります。
坐骨神経痛においては、骨盤や腰椎の歪みを調整し、周囲の筋肉の緊張をゆるめることで神経の通り道を正常に保つことを目指します。
特に仙腸関節や腰椎4番〜5番の可動性低下が関与していることが多く、これらの調整は坐骨神経痛の軽減に直結します。
さらに、梨状筋の過緊張もよく見られる原因のひとつです。
梨状筋は坐骨神経と交差するため、この筋肉が緊張することで神経を圧迫してしまうことがあります。
整体では、骨盤周辺のアライメントを整えると同時に、梨状筋や大腿筋膜張筋などの柔軟性を取り戻す手技が用いられます。
近年では、筋膜リリースやトリガーポイント療法といった技術も併用されることが増えており、従来の「ボキボキする」整体とは異なる、よりソフトかつ科学的な手法が主流になりつつあります。
これにより、神経過敏になっている人や高齢者にも安全に施術できる環境が整っています。
整体による改善効果に関しては、統計的な裏付けも徐々に蓄積されてきています。
例えば、2019年に発表された国内の臨床調査では、慢性坐骨神経痛に対する骨盤調整と筋肉へのアプローチを組み合わせた施術を4週間継続した結果、約7割の患者で痛みの軽減と可動域の向上が確認されたと報告されています。
重要なのは、整体を受ける側の姿勢です。
痛みのある部位だけでなく、全身のバランスに意識を向けること、そして日常生活での姿勢や動作を見直すことも施術効果を持続させるために必要です。
整体は「治してもらう」場ではなく、「体の使い方を学び、自ら改善する」ためのパートナーであるという認識が求められます。
症状の根本にアプローチする整体は、薬に頼らずに痛みを軽減したい人にとって大きな希望となる方法です。
定期的なケアと生活習慣の見直しを組み合わせることで、坐骨神経痛の改善と再発予防の両立が期待できます。
6.坐骨神経痛と関連する腰痛の違いについて
現代人の生活はデジタル化やリモートワークの普及により、運動量が著しく減少しています。
この「運動不足」は、坐骨神経痛の悪化を招く大きな要因の一つです。
単なる体力低下にとどまらず、筋肉や関節、神経に及ぼす影響を通じて痛みやしびれを慢性化させてしまうリスクが高まります。
まず、運動不足により骨盤周囲の筋肉、特に大臀筋・中臀筋・梨状筋といった深層筋が弱化します。
これらの筋肉は、骨盤を安定させ、坐骨神経の通り道を確保する役割を果たしています。
筋力が落ちると骨盤が前傾または後傾しやすくなり、腰椎に不自然な負荷がかかることで、椎間板や神経根への圧迫が起こりやすくなります。
また、長時間の座位姿勢が続くと、臀部の筋肉が過度に圧迫され、筋膜の滑走性が低下します。
これが梨状筋症候群などの二次的な神経圧迫の引き金となることがあります。
特にオフィスワーカーやドライバーなど、1日8時間以上座っている人は注意が必要です。
ある海外の研究では、1日6時間以上座り続ける人は、坐骨神経痛発症のリスクが約1.4倍高いと報告されています。
さらに、運動不足による血流低下も見逃せません。
筋肉が動かないと血液循環が悪化し、老廃物が滞留しやすくなります。
これが神経への慢性的な刺激となり、痛みや炎症を長引かせる要因になります。
特に坐骨神経は長く伸びた末梢神経であり、酸素や栄養の供給が不足すると過敏化しやすいのです。
自律神経への影響も無視できません。
運動を通じて交感神経と副交感神経のバランスが保たれますが、運動不足が続くとこのバランスが崩れ、痛みの閾値が下がることがあります。
つまり、通常なら気にならないような刺激にも過剰に反応してしまい、慢性的な坐骨神経痛に移行してしまうリスクがあるのです。
加えて、姿勢の悪化も深刻な問題です。
運動をしないことで、体幹を支える筋肉が機能低下し、猫背や反り腰といった悪い姿勢が定着しやすくなります。
姿勢の乱れは背骨のアライメント異常を引き起こし、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、坐骨神経痛の原因となる疾患を誘発する要因になります。
このように、運動不足は筋力低下、血流障害、姿勢悪化、自律神経の乱れといった複数の経路から坐骨神経痛に悪影響を与えます。
1日30分の軽い運動でも、これらのリスクを大きく減らすことが可能です。
忙しくても、エレベーターではなく階段を使う、座りすぎたら1時間ごとに立ち上がって体を動かすなど、小さな意識の積み重ねが大切です。
8. 坐骨神経痛に効果的なストレッチ方法を紹介
坐骨神経痛の緩和や再発予防には、適切なストレッチが非常に有効です。
ただし、誤った方法で行うと逆に症状を悪化させる恐れがあるため、効果的なストレッチ方法を理解し、正しく実践することが重要です。
ここでは、坐骨神経に関連する筋肉に焦点を当てた実践的なストレッチ方法を紹介します。
まず注目すべきは梨状筋のストレッチです。
梨状筋は骨盤から大腿骨へとつながる筋肉で、坐骨神経のすぐ近く、または貫通して走行することがあります。
この筋肉が緊張すると坐骨神経を圧迫し、典型的なしびれや痛みの原因となります。
梨状筋ストレッチの一例として、仰向けに寝て膝を立て、片脚の足首を反対側の膝の上に乗せ、手で太ももを引き寄せるポーズがあります。
約20〜30秒キープし、左右交互に行うのが効果的です。
次に大臀筋のストレッチも欠かせません。
大臀筋はお尻の表層にある大きな筋肉で、体の安定や歩行に深く関与しています。
これが硬くなると骨盤の動きが悪くなり、間接的に坐骨神経への負担が増加します。
椅子に浅く座り、片膝を反対の太ももに乗せた状態で前傾するストレッチは、大臀筋の柔軟性を高めるのに非常に効果的です。
さらに、ハムストリングス(太もも裏の筋肉)の柔軟性も重要です。
ハムストリングスが硬いと骨盤が後傾しやすくなり、腰椎のカーブが不自然になって神経に影響を及ぼします。立ったまま前屈して片足を台に乗せ、背筋を伸ばしたまま前に倒れる動作を取り入れると、安全かつ効果的にハムストリングスを伸ばせます。
ストレッチを行う際は、呼吸を止めないことが大切です。
痛みを感じる直前でキープし、リラックスした呼吸を続けることで、副交感神経が優位になり、筋肉が自然にゆるんでいきます。
また、1日数回、決まった時間に行うことで、神経と筋肉の記憶に定着しやすくなります。
なお、急性期の強い痛みやしびれがある場合は無理にストレッチをせず、専門家に相談することが推奨されます。
ストレッチは万能ではなく、症状に応じて適切な段階で導入することが求められます。
近年の研究でも、ストレッチは坐骨神経痛の改善に有効であることが示されています。
2020年に国内で行われた研究では、週に3回以上のストレッチを4週間続けたグループが、痛みの軽減率と生活の質(QOL)の改善スコアで他群より有意に高い数値を示しました。
正しいストレッチの習慣化は、坐骨神経痛のセルフケアにおける最もシンプルかつ有力な手段です。
継続こそが鍵であることを忘れずに取り組むことが大切です。

9. 市販薬と整体を併用した坐骨神経痛ケアのポイント
坐骨神経痛の痛みやしびれが強いとき、市販薬で一時的に症状を抑えつつ、根本改善を目指す整体を併用する方法は非常に有効です。
ただし、その併用にはいくつかの注意点があり、正しい知識を持って取り組まなければ期待される効果が得られないばかりか、逆に症状を長引かせることもあります。
市販薬として多く利用されているのは、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンを主成分とする鎮痛薬です。
これらは炎症を抑えたり、痛みを一時的に軽減する効果があります。
具体的には、イブプロフェンやロキソプロフェンといった成分が代表的です。
厚生労働省の統計によると、腰痛や坐骨神経痛に対する鎮痛薬の市販利用率は全体の約42%に上るというデータがあります。
これらの薬は確かに即効性がありますが、痛みの原因にアプローチするわけではありません。
坐骨神経痛が椎間板の変性や骨盤の歪み、筋肉の緊張によって引き起こされている場合、薬で一時的に症状を抑えても、根本的な問題は解消されないため、再発しやすくなります。
その点で、整体は神経への圧迫を引き起こす構造的な問題に対して、骨格や筋肉を整えることによってアプローチする手段です。
薬によって痛みが抑えられている状態で整体を受けることで、筋肉がリラックスしやすくなり、施術効果が高まりやすいという相乗効果が期待できます。
ただし、薬を使用した直後のタイミングでの強い刺激や矯正は注意が必要です。
痛みが感じにくくなることで、施術中に体への負担を過小評価してしまうリスクがあるからです。
必ず信頼できる施術者と相談しながら、薬の使用タイミングと施術内容を調整することが求められます。
また、外用薬や温感湿布を併用するケースもあります。
これらは血行を促進し、筋肉の緊張を緩和する効果が期待できますが、皮膚への刺激やアレルギー反応に注意しなければなりません。
複数の市販薬を同時に使用することは避けるべきで、併用時には医師や薬剤師に相談することが望ましいです。
心身の両面からアプローチすることも大切です。
痛みが続くと心理的なストレスや不安感が増し、これが交感神経を過剰に刺激して痛みの悪循環を引き起こします。
薬と整体を併用することによって「今は治療している」という安心感が得られ、精神的な面でも安定しやすくなるのです。
最終的に大切なのは、薬に依存しすぎず、体の本来持つ回復力を引き出す方向に意識を向けることです。
市販薬はあくまで一時的なサポート手段と位置づけ、整体やストレッチ、生活習慣の改善と組み合わせることで、坐骨神経痛に対する包括的なケアが実現できます。
10. 坐骨神経痛の再発を防ぐ生活習慣の整え方
坐骨神経痛は一度改善しても、再発するケースが非常に多い疾患です。
実際、腰痛や坐骨神経痛を経験した人の約60%が、数年以内に再発を経験しているという報告もあります。
そのため、治療後に重要になるのが「予防を意識した生活習慣の構築」です。
坐骨神経痛を繰り返さないためには、日々の行動を見直し、身体に優しい生活スタイルを取り入れることが鍵となります。
まず最も基本的な習慣が「正しい姿勢の維持」です。
特に長時間のデスクワークを行う方は、猫背や前傾姿勢になりがちです。
これが骨盤の歪みや腰椎への負荷を高め、坐骨神経への圧迫につながります。椅子に深く座り、骨盤を立てて背筋を伸ばすこと。
モニターの高さを目線に合わせること。足裏をしっかり床に着けること。
こういった基本的な姿勢を意識するだけで、坐骨神経への圧力を大幅に軽減できます。
次に重要なのが「定期的な運動」です。
特に推奨されているのは、ウォーキングやストレッチ、体幹トレーニングなどの軽度~中程度の運動です。
筋力を維持・強化することは、骨格を安定させ、坐骨神経痛の根本原因となる骨盤や脊椎のバランス崩れを予防するうえで非常に有効です。
週に150分以上の中強度運動が推奨されており、これは1日約20〜30分の散歩でも十分に達成可能です。
睡眠の質を高めることも、坐骨神経痛の再発防止に直結します。
寝具の硬さが適切でないと、寝ている間に腰や臀部に余計な圧力がかかり、筋肉が硬直しやすくなります。
特にマットレスは、柔らかすぎても硬すぎてもNGです。
適度な反発力があり、体の自然なS字カーブを支えてくれるものを選ぶことが望ましいです。
また、寝る前のスマホ使用を控え、自律神経のバランスを整える習慣を意識することも重要です。
さらに「体重管理」も見逃せない要素です。
体重が増えると、それだけ腰椎や骨盤、下肢にかかる負担が大きくなり、坐骨神経の周辺組織にもストレスが蓄積します。
BMIが25を超える肥満体型の人は、標準体型の人に比べて坐骨神経痛の発症率が1.7倍以上高いという報告もあります。
食事の内容を見直し、栄養バランスを整えるとともに、過剰なカロリー摂取を控える工夫が求められます。
精神的ストレスへの対処も重要です。
ストレスは筋緊張を高め、血流を悪化させ、交感神経の過活動を促進します。
その結果、坐骨神経痛の慢性化や再発リスクが高まることがわかっています。
日常的にリラクゼーション法(深呼吸、瞑想、ヨガなど)を取り入れることは、神経系の安定と痛みのコントロールに大いに役立ちます。
生活環境の工夫も忘れてはいけません。
例えば、重い荷物を持ち上げるときには、必ず膝を曲げて腰を落とす。
家事や育児で中腰姿勢が多い場合は、こまめに休憩を挟み、ストレッチで筋肉をリセットする。
靴は足にフィットし、衝撃吸収に優れたものを選ぶ。
こうした小さな選択の積み重ねが、長期的には大きな健康差を生み出します。
また、定期的に身体の状態をチェックする習慣も大切です。
軽度の違和感や疲労を放置せず、早めに対応することが、再発の芽を摘む最大の予防策となります。
日記やアプリで体調の変化を記録し、日々の行動との因果関係を把握しておくと、再発リスクの高い行動を特定しやすくなります。
このように、坐骨神経痛の再発予防は単なる治療の延長ではなく、「身体と向き合う生活習慣の再構築」そのものです。
自分の身体を守る意識を持ち、今日からできる小さな改善を積み重ねることが、坐骨神経痛のない快適な未来へとつながっていくのです。